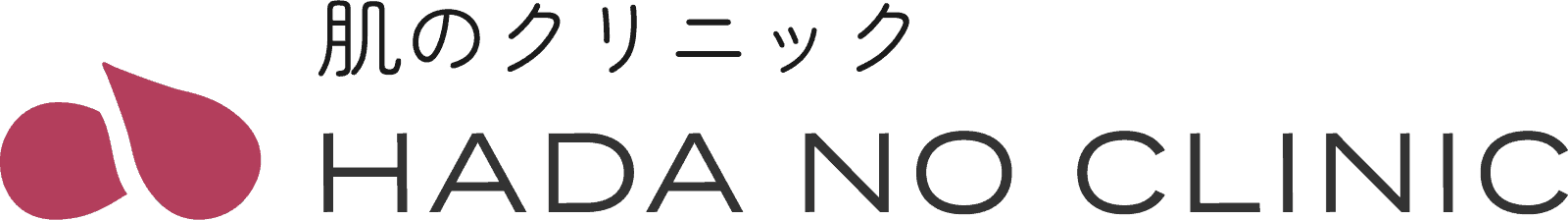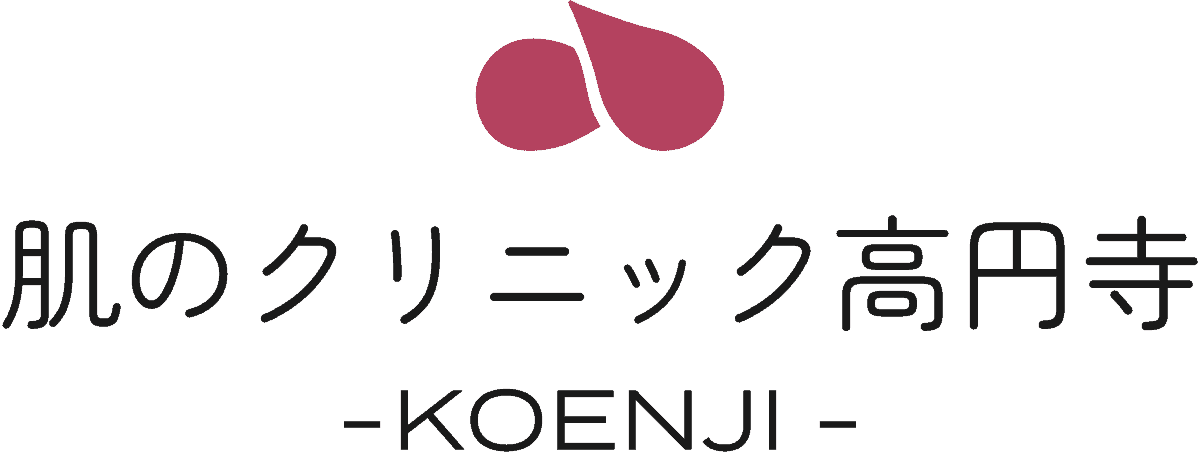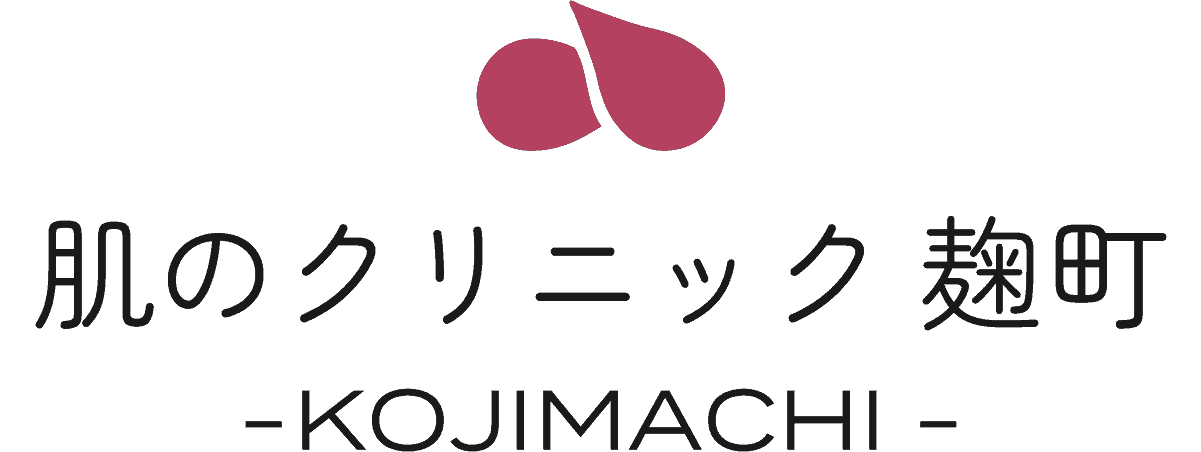「太っている人は、意志が弱いからだ」
この言葉を耳にしたことはありませんか?あるいは自分自身にそう言い聞かせて、毎日自分を責め続けてきた方もいるかもしれません。
私は医師として患者さんのダイエット治療をしていく中で、「意志の強さ」と「食欲のコントロール」は全くの別問題だと確信しています。そして私自身、マンジャロ(チルゼパチド)を使用して12kgの減量に成功した経験から、その確信はさらに強まりました。
今回は、なぜ食欲が単なる「我慢」の問題ではないのか、そしてマンジャロが私の体重と生活をどう変えたのか、最新の医学的知見と自身の体験からお伝えします。
「食欲だけは我慢できて当たり前」という大きな誤解
私たち人間には、様々な生理的欲求があります。例えば、眠気・排泄欲・痛み・寒さ暑さへの反応など—これらはすべて、命を守るための本能的な反応です。
あなたは眠気を永遠に我慢することができますか?答えはもちろん「No」でしょう。いくら頑張っても、最終的には眠ってしまいます。排泄も同じで、一時的に我慢はできても、最終的には限界がきます。
不思議なことに、「食欲」だけは「我慢できて当たり前」という価値観が社会には根強くあります。なぜこのような誤解が生まれるのでしょうか?
答えは意外にシンプルです。単に「コントロール可能な範囲の食欲」しか感じたことがない人が大勢いるからです。人は他人の感情を完全に理解することはできません。自分が経験したことのない強い欲求を、他人が感じているとは想像できないのです。
私の体験:マンジャロで12kgの減量に成功
私は糖尿病の家系に生まれ、母方の祖父母はどちらも糖尿病を患っていました。その遺伝背景からか、自身も「コントロールできない食欲」という見えない敵と闘っていました。
そこで、食欲のコントロールにマンジャロを試してみることにしました。マンジャロ(チルゼパチド)は、GLP-1だけでなくGIPの受容体も活性化させる「二重作動薬」であり、従来のGLP-1製剤よりも強力な効果を示します。詳しくは、前回の記事『GLP-1ダイエット – 医師が解説する「痩せる注射」の真実』もご覧ください。
マンジャロ使用の実際




私のマンジャロ使用体験を具体的にお伝えします:
- 投与量と期間:最初の2ヶ月は2.5mgを1週間に1回注射
- 初期症状:最初の数回は軽い動悸や気持ち悪さを感じました(これは患者さんもよく訴える症状です)
- 安全性:血液検査では低血糖症状はなく、肝機能や腎機能、甲状腺検査等の項目も正常値でした
- 増量:3ヶ月目からは体が慣れてきたこともあり、5mgへ増量しました
- 効果:わずか3ヶ月で80kg→68kgへ12キロの体重減少に成功
- 併用療法:この結果は運動療法と食事療法を併せた総合的な取り組みによるものです
最も驚いたのは、自分の「意志の強さ」はまったく変わっていないのに、「食欲の強さ」だけが変化したことです。以前は自分の意志ではどうにもならないほどの強い食欲に悩まされていましたが、マンジャロを使うことで、その過剰な食欲が自然と落ち着き、無理なく食事量を調整できるようになりました。
「食事を我慢する」というより「そこまで欲しくない」から自然と減る。この違いは、想像以上に大きなものでした。体も軽くなり、運動も続けやすくなり、良い循環が生まれていったのです。
それまでは、どれだけ強い意志を持っても、どうにもならない瞬間がありました。それほどまでに「本能から湧き上がる欲求」は、時に人間の理性を簡単に超えてしまうのです。
マンジャロについて、詳しくは肌のクリニックのダイエット治療外来をご覧ください。
私が体験したマンジャロの効果
- 食欲の自然な低下:特に甘いものや脂っこいものへの欲求が激減しました。ケーキや揚げ物を見ても「別にいいや」と思えるようになったのです。
- 食後の眠気が消失:昼食後に襲われていたあの強烈な眠気がほぼなくなりました。午後の仕事の効率が格段に上がりました。
- 空腹感のコントロール:「お腹がすいた」と感じても、以前のような切迫感や苦痛がなくなりました。理性的に「そろそろ食事の時間だな」と判断できるようになったのです。
- 集中力の向上:血糖値の乱高下がなくなったことで、思考がクリアになり、集中力が持続するようになりました。
- 体重減少:3ヶ月で12kgの減量に成功しました。しかも、無理な食事制限や空腹との戦いなしに達成できたのです。
マンジャロで気をつけるべきこと:私の経験から
マンジャロは効果的な治療法ですが、使用する際にはいくつか注意点があります。私自身の経験も踏まえてお伝えします。
- 1. 副作用について
-
マンジャロを使い始めてから1週間ほどは、軽い吐き気を感じることがありました。これは多くの方に見られる初期症状ですが、徐々に慣れていきます。また、便秘傾向になることもあるため、水分と食物繊維をしっかり摂ることをお勧めします。
- 2. 栄養バランスに注意
-
食欲が低下すると、必要な栄養素が不足するリスクがあります。特にタンパク質とビタミン・ミネラルの摂取には意識的に取り組む必要があります。私の場合は、プロテインシェイクや栄養補助食品を活用していました。
- 3. 継続的な医療管理の必要性
-
自己判断での使用は危険です。必ず医師の指導のもとで使用し、定期的に検査や診察を受けることが重要です。副作用や効果の経過をモニタリングすることで、より安全で効果的な治療が可能になります。
- 4. 生活習慣の見直し
-
マンジャロは、食生活の改善や適度な運動と組み合わせることで、最大の効果を得ることができます。マンジャロ効果を最大化する食事・運動療法については「GLP-1ダイエット中の痩せる体質を作る運動・栄養法」をご覧ください。
- 5. 食事と運動習慣の継続
-
マンジャロは「魔法の薬」ではありません。中止後は食欲は徐々に元に戻り、リバウンドしやすくなります。食事記録を取り、マンジャロをやめたあとも同じ食事量と運動量を継続してください。
食欲コントロールの科学 – なぜ意志の力だけでは難しいのか
糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きが弱くなったり、分泌量が足りなくなったりすることで、血糖値が慢性的に高くなる病気です。
この「インスリンを出す力(=膵臓の分泌予備能)」は、人種や個人によって大きな差があります。この能力が低いほど、食後の血糖値が高いまま長く続いてしまうのです。
また、腸から分泌されるGLP-1やGIPといった消化管ホルモンは、血糖値に応じてインスリン分泌を助ける働きをしますが、これらの分泌が弱い場合も、同様に食後高血糖が続きやすくなります。この「食後高血糖」は、眠気や集中力の低下を引き起こし、さらにその後の血糖値の急降下によって、強い空腹感=食欲の亢進が生じるのです。
反対に、GLP-1やGIPといったホルモンがしっかり分泌され、膵臓のインスリン分泌力も十分にある場合、血糖値の上昇は穏やかに抑えられ、安定した状態が続きます。この結果、食後の眠気も軽く、食欲も自然とコントロールしやすくなるのです。
食後高血糖と眠気の意外な関係
「食後の眠気」、特に昼食後に襲われるあの強烈な眠気に苦しんだ経験はありませんか?実はこれも、食欲のコントロールと密接に関連しています。マンジャロを使い始めてから、食後の眠気も劇的に改善したのを実感しました。
オレキシンと覚醒のメカニズム
私たちが目を覚まして活動していられるのは、「脳の覚醒系」と呼ばれる神経ネットワークのおかげです。この覚醒系の中で重要な役割を果たすのが「オレキシン」という神経伝達物質です。
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の柳沢正史教授によって発見されたこのオレキシンは、脳の視床下部から分泌され、脳全体の覚醒レベルを高める働きをします。オレキシンが欠乏すると「ナルコレプシー(突発性睡眠症)」という病気を引き起こすほど、私たちの覚醒にとって重要な物質なのです。
血糖値とオレキシンの関係
最新の研究によると、血糖値が高くなると、オレキシンを産生している神経が活動を休止してしまうことが分かっています。
つまり、食後に血糖値が急上昇すると、脳のオレキシン神経が静かになり、その結果として私たちは眠気を感じやすくなるのです。これは「お昼ごはんの後に眠くなる理由」にもピッタリ当てはまります。炭水化物中心の食事を摂ると血糖値が急に上がりやすく、その結果、オレキシンの働きが弱まってしまうのです。
さらに厄介なことに、血糖値が急上昇した後には急降下することがあり、これが強烈な空腹感を引き起こします。この現象は「リアクティブハイポグライセミア(反応性低血糖)」と呼ばれ、「またすぐに何か食べたい」という強い衝動につながります。
こうして「食べる→眠くなる→血糖値が下がる→また強く食べたくなる」という悪循環に陥りやすくなるのです。マンジャロにより血糖値の急上昇が抑えられることで、この悪循環が断ち切られ、昼食後の眠気も減少し、午後の活動も充実するようになりました。
「太ること」は人間の進化の歴史から見ると当然の行動
今、肥満や中年太りに悩んでいる方の中には、自分の意志の弱さを責めてしまう方もいるでしょう。しかし、それは人間として「当然の反応」なのです。
私たち人類は、長い歴史の中で「飢餓」と戦ってきました。食べ物が手に入らない環境では、「強い食欲」が生き残るために絶対に必要でした。食べられるときにできるだけ食べて脂肪として蓄える—その能力が高い個体が、次世代へと命を繋いできたのです。
問題は、このプログラムが「飽食の時代」と言われる現代にも、私たちの体に組み込まれたままだということ。かつては生存のために必須だった「食欲」が、今では「生活習慣病のリスク」となっているのです。
病気になる前にこそ、医療の力を
日本の医療システムは、世界的に見ても非常に優れています。公的医療保険によって多くの人が高額な治療を受けることができ、医療の質も高い水準で保たれています。
しかし、このシステムには一つ大きな盲点があります。それは、「まだ病気と診断されていない人」、つまり健康と病気の間にいる人たちへのアプローチが乏しいことです。
糖尿病と診断された瞬間から、医療は手厚くなります。薬が処方され、血糖値は厳密に管理され、様々な指導が行われます。しかし、「その一歩手前」にいる人たちに対しては、”それは自己責任だ”という冷たい現実が突きつけられるだけです。
「病気の定義」に含まれない方々には医療のサポートはほとんど存在せず、保険診療の対象にもなりません。これが「予防医療」の大きな壁となっています。
多くの人々が本当に望んでいるのは、「病気になってからの治療」ではなく、「病気にならないための手助け」です。その観点から考えると、マンジャロをはじめとするGLP-1製剤による食欲コントロール治療は非常に価値のあるアプローチです。
高血圧や高脂血症、糖尿病といった生活習慣病の多くは、「食べすぎ」や「体重増加」によって引き起こされます。これらを未然に防ぐためには、「食べすぎない」状態を無理なく自然に続けられることが理想的です。
まとめ:食欲は意志の問題ではない
「太っている人は意志が弱い」という考え方は、科学的に見て大きな誤りです。食欲は複雑な生理的メカニズムによって制御されており、個人差が大きいことがわかっています。
特に日本人は食後高血糖になりやすい体質を持っており、これが強い眠気や過剰な食欲につながっている可能性があります。マンジャロ(チルゼパチド)はこうした生理的なメカニズムに直接働きかけることで、無理なく食欲をコントロールする可能性を開いています。
私自身の12kgの減量体験からも言えるのは、重要なのは自分や他人を「意志が弱い」と責めるのではなく、それぞれの体質や生理的な特性を理解し、必要であれば医療の力も借りながら、健康的な生活を目指すことです。
マンジャロが教えてくれたのは、「意志の力だけで食欲と闘う必要はない」ということ。医学の力を借りることで、無理なく自然に、健康的な食習慣を手に入れることができるのです。
食欲のコントロールに悩んでいる方は、決して一人ではありません。今回お伝えした内容が、少しでも皆さんの理解の助けになれば幸いです。
医師 先間 泰史(編集:院長 岩橋 陽介)
参考文献・サイト一覧
- Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM, et al. Obesity pathogenesis: an endocrine society scientific statement. Endocrine Reviews. 2017;38(4):267-296.
- Sumithran P, Proietto J. The defence of body weight: a physiological basis for weight regain after weight loss. Clinical Science. 2013;124(4):231-241.
- Sakurai T. The role of orexin in motivated behaviours. Nature Reviews Neuroscience. 2014;15(11):719-731.
- Yamanaka A, Beuckmann CT, Willie JT, et al. Hypothalamic orexin neurons regulate arousal according to energy balance in mice. Neuron. 2003;38(5):701-713.
- Tominaga, M., Eguchi, H., Manaka, H., et al. (1999). Impaired glucose tolerance is a risk factor for cardiovascular disease, but not impaired fasting glucose. The Funagata Diabetes Study. Diabetes Care, 22(6), 920-924.
- Tsujino N, Sakurai T. Orexin/hypocretin: a neuropeptide at the interface of sleep, energy homeostasis, and reward system. Pharmacological Reviews. 2009;61(2):162-176.
- Willie JT, Chemelli RM, Sinton CM, Yanagisawa M. To eat or to sleep? Orexin in the regulation of feeding and wakefulness. Annual Review of Neuroscience. 2001;24:429-458.
- Chemelli RM, Willie JT, Sinton CM, et al. Narcolepsy in orexin knockout mice: molecular genetics of sleep regulation. Cell. 1999;98(4):437-451.
- DECODE Study Group. (1999). Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. The Lancet, 354(9179), 617-621.
- Blundell JE, Finlayson G. Is susceptibility to weight gain characterized by homeostatic or hedonic risk factors for overconsumption? Physiology & Behavior. 2004;82(1):21-25.